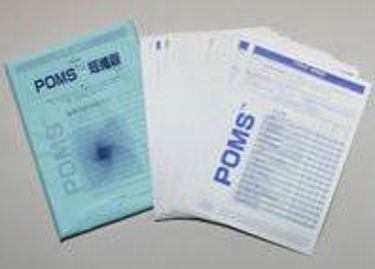私共の研究グループでは質問紙(アンケート)で天然物の機能性を評価する事例が多数あります。約15年くらい前より、食品だけでなく香りや化粧品なども質問紙で評価を実施してきました。
筆者は元々メタボリックシンドロームの研究者であったのですが、それから脳科学に興味を持ち、現在では質問紙が手放せない存在になっています。
私が脳科学に至った変遷。
— 大貫教授@食品研究者 (@k_ohnuki) March 20, 2019
ダイエットの研究で博士
↓
会社でダイエット食品の提案
↓
食欲抑制に大きな効果
↓
抗鬱サプリに食欲抑制の効果
↓
食欲抑制と抗鬱に共通の仕組み
↓
会社の人間関係で鬱
↓
鬱に関する研究したい!
↓
会社を辞めて脳研究に飛び込む
↓
さらに鬱な環境
↓
なんとか独立