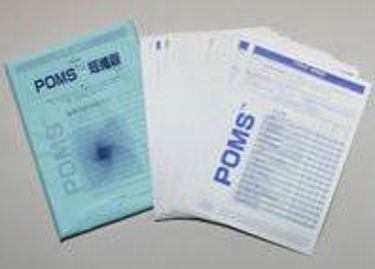弊社は主に健康食品の臨床試験を受託していますが、業務の1~2割程度、化粧品に関する受託もしています。化粧品に関する本研究チームの状況をご紹介します。
食品の学者が化粧品の研究も実施している理由。
— 大貫教授@食品研究者 (@k_ohnuki) May 22, 2019
・共通する研究手法が多い
・食べて良いものは肌にも良いことが多い
・食品と化粧品の双方扱う企業も多い
肌から摂取する、といったイメージでしょうか?
約10年をかけて、細胞レベルから臨床試験まで実施できる体制が整いました。
化粧品研究の概要
ヒト試験(臨床試験)の進め方としては、肌に効果があるサプリメントは、概ね同様な方法で進められています。
化粧品の効果を検証する研究方法。
— 大貫教授@食品研究者 (@k_ohnuki) May 23, 2019
最も分かりやすいのは、臨床試験と呼ばれる、実際に多くの方々に試用してもらう方法です。
肌に効果のあるサプリメントに関する研究でも使われています。
化粧品は、試用する量や頻度などで効果が変わるので、食品より難しいです。https://t.co/4wTuGBFc9R
化粧品は、健康食品のように機能性表示食品のような制度がないので、in vitro試験(酵素活性や細胞実験など)で検証することも多いです。
化粧品開発の基礎研究メニューとして、以下のような研究を実施しています。
— 大貫教授@食品研究者 (@k_ohnuki) May 24, 2019
・リパーゼ阻害活性(ニキビ、炎症)
・チロシナーゼ阻害活性(美白)
・コラゲナーゼ活性(シワやたるみ)
・抗酸化力(同上)
開発だけでなく、その結果を広報に使われている場合も多いです。
コラゲナーゼ(コラーゲン分解酵素)活性については、Youtubeに動画をアップロードしています。
コラーゲン分解を抑える食品や化粧品に関する研究は、その分解酵素の活性を測定します。
— 大貫教授@食品研究者 (@k_ohnuki) May 25, 2019
コラーゲンはそのまま塗布や摂取しても体内に入れるのは困難なので、分解酵素を抑えることが、コラーゲンを失わずに済むことになります。
シワなどへの効果が期待されます。https://t.co/MsThMKd21v
効果検証の実情
実際に効果を検証すると、プラセボとの比較で効果を検出できないことも少なくありません。
約20年前にアトピー性皮膚炎と診断され、今では日常生活への支障はほどんどないですが、皮膚症状とは長いお付き合いです。
— 大貫教授@食品研究者 (@k_ohnuki) June 10, 2019
その際に助かるのは、効果検証の際に余ったプラセボ(特別な有効成分を含まない)化粧水です。
必要最小限な成分を含み、丁寧に作られた化粧品は、万人におススメできます。 pic.twitter.com/cQReugJrGz
化粧品会社の方にとっては都合の良い話ではないですが、プラセボが良く効いて、肌にも優しいように思います。プラセボで、うつ状態や不安感、痛みなども改善しやすいのですが、皮膚科医の話によると、イボも治ってしまうという研究もあるようです。まさに、病は気からですね。
— 大貫教授@食品研究者 (@k_ohnuki) June 16, 2019
私共の研究が上手くいっていない訳ではなく、食品では効果のある製品を多く検出しています。
最近、肌質を改善(保湿やメラニンの抑制など)するサプリメントの効果を多く検出することができました。まだ公表できないのですが、半年後くらいには紹介できると思います。一方、化粧品の効果を検出するのはかなり難しいです。プラセボ(特殊な有効成分を含まない化粧品)が良く効いてしまいます。
— 大貫教授@食品研究者 (@k_ohnuki) June 16, 2019
最近、肌質を改善(保湿やメラニンの抑制など)するサプリメントの効果を多く検出することができました。まだ公表できないのですが、半年後くらいには紹介できると思います。一方、化粧品の効果を検出するのはかなり難しいです。プラセボ(特殊な有効成分を含まない化粧品)が良く効いてしまいます。
— 大貫教授@食品研究者 (@k_ohnuki) June 16, 2019
個人的には、肌に関するケアは、化粧品に加えて、サプリメントもお勧めしたいと思います。
肌質の改善(保湿、メラニン抑制、炎症抑制など)に関するヒト試験を十数本実施してきましたが、これまでのところ、化粧品よりも食品成分の方が改善効果がありました。まだ、主な化粧品成分を試してきた訳ではないですが、身体の中からキレイにするというコンセプトは間違いないようです。
— 大貫教授@食品研究者 (@k_ohnuki) September 4, 2019
もちろん、スキンケアに化粧品は必要不可欠であることには間違いありませんが、一定レベル以上の製品に大きな改善効果を求めることは難しいという印象です。
特別な効果検証の事例
前述の通り、食品のような制度がなく、肌に対する一般的な効果検証よりも、それぞれ個性のある依頼をされることが多いように思います。
今までの面白い研究の1つに『妊活化粧品』があります。
— 大貫教授@食品研究者 (@k_ohnuki) September 3, 2019
若返りホルモンと呼ばれたり、不妊の方にも使われているDHEAというホルモンが、ある化粧品を使うことで増加する結果を出すことができました。
その成分など詳細を教えてもらえないことが残念ですが、香り成分に秘密があるようでした。
モンドセレクションの事例は、機能性表示食品のように、申請をするための効果検証と言えるかもしれません。プラセボ比較は必要なく、前後比較でも大丈夫のようで、かなり安価に実施できます。
化粧品にもモンドセレクションがあります。
— 大貫教授@食品研究者 (@k_ohnuki) May 26, 2019
お菓子のイメージが強いですが、メーカーさんより依頼を受けて初めて知りました。
具体的な申請方法などは知らないですが、評価試験が必要とのことで、簡単な実験を実施しました。
何となく美味しそうな、食べても良さそうなイメージになりそうです。