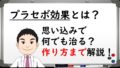目次
産学連携での論文の活用
研究論文依頼の多くが機能性表示食品の届出に必要になるからですが、上手く活用されている企業もあります。
研究論文には大学名が書ける!
学術論文を知っている方々には当たり前と思いがちですが、意外と盲点な事実だと気付きました。 国公立大学は 特に 保守的な場合が多く、研究成果と大学名を結び付けることを極端に嫌う場合があります。研究論文には、堂々と大学名(所属)を記載することができて、都度大学に許可をもらうことも不要です。企業の方との共同発表にする形も問題なく可能であることが多く、一般的に困難なことが、論文で解決することもあるように思いました。
論文をWebサイトに掲載できない?
前述の通り、論文執筆費用をご負担頂いたにもかかわらず、著作権は出版元になることがほとんどです。そのため、全文を掲載することや自社サイトでPDFをダウンロードできるようにすることは著作権法違反になります。
研究者は日常的に使っている論文紹介の方法ですが、「引用」であれば全く問題ありません。論文の一部を掲載、または要約した表現を記載して、論文の情報を記載するといった具合です。
臨床試験を委託して頂いた場合、自社で出したデータについては、もちろんそのデータをWebサイトに出すことは可能です。学術的に正しい情報を一人でも多くの方に届けるために、広報活動には最大限ご協力させて頂きたいと思います。
論文にすると特許が出せない?
結論からお伝えしますと、研究論文を投稿しても、特許を出すことができます。 詳細は特許庁のホームページなどが参考になるかと思います。
特許庁の情報にあります通り、論文を投稿することは公知の事実になってしまいますので新規性や進歩性を喪失することになってしまいます。1年間の猶予がありますが、特許戦略も考えて論文投稿をしたことが良いことは、確かです。
論文執筆の受託:費用や納期など
論文を依頼される際には、 上記のような状況を踏まえ、ご要望を事前にお伝え頂けると誤解のない意図される通りの論文に近付くのではと思いました。事務的にご留意頂く点を以下、列挙させて頂きました。
・費用は一律、日本語論文50万円、英語論文100万円
・納期は 日本語論文4ヶ月、英語論文6ヶ月 (完了次第納品します)
・業務の範囲は論文執筆まで、確認頂いた後に無償で論文投稿と審査対応
(投稿しないという選択肢もあります)
・原則事前請求もしくは論文完成時までに精算
・訂正は表現に関する部分を原則1回のみ
(複数回の修正や、原則、グラフや結論の訂正はお断りします)
・掲載料が別途必要(5~30万円が相場です)
論文執筆の依頼が多くなることに対応できるよう、当研究チームでは、教員レベル(教授や准教授経験者含む)の研究者を多く抱えております。自社試験、他社の試験についても論文化可能であり、それらの論文化に関するご相談も歓迎です。
お問い合わせ(お申し込み)
以下、メールやLINEにてお問い合わせ頂けますと弊社よりご連絡させて頂きたいと思います(その他、電話等でのお問い合わせは現在受け付けておりません)。お手数をお掛けしますが、宜しお願い致します。
LINEを使ったお問い合わせ
以下のQRコードを使って友だち追加して頂けますと、「食品機能学研究室」というアカウントに繋がります。そちらにメッセージをお送り頂けますと弊社スタッフもしくは研究内容の理解できる連携研究者よりお返事させて頂きたいと思います。

メールでのお問い合わせ
以下のフォームにご入力頂けましたら、弊社スタッフもしくは研究内容の理解できる連携研究者よりメールにてお返事させて頂きたいと思います(フォームにご入力頂けると弊社にメールが届きます)。最後に送信ボタンをお忘れないようお願い致します。