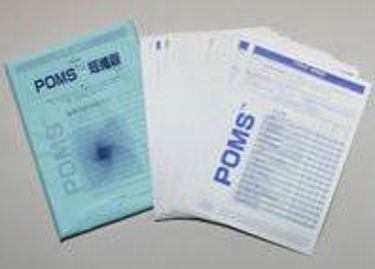食品の機能性とは?
例えば携帯電話には、通話機能や通信機能、カメラ機能などを求めることと思います。しかしながら、食品に対して機能を意識することはあまりないかもしれません。
食品の一次機能、二次機能、三次機能
食品には以下のような機能があると言われています。
一次機能:栄養機能
二次機能:嗜好性
三次機能:生体調節機能
私たちは、生きるために、エネルギー源や必要な物質を欠乏しないように食物を摂取しています。栄養素を摂取するための機能を食品の一次機能と言います。また、美味しい、好きである食品を選ぶと思います。食品の嗜好性、美味しさは二次機能とされています。
機能性食品
食品の機能には、栄養機能や嗜好性もありますが、特に食品の三次機能を高めた食品を機能性食品と呼びます。例えば、メタボリックシンドロームを予防する、便通を促進する等、身体の様々な諸問題を解決するような食品です。以下のような食品がその一例です。
希少糖・オリゴ糖・食物繊維:血糖値上昇抑制、便通の促進など
アミノ酸:睡眠、疲労感、メンタルヘルス改善など
ペプチド類:高血圧の予防など
脂肪酸:認知機能改善など
ポリフェノール類:メタボリックシンドロームの予防など
香辛料成分:代謝を高めるなど
このページで紹介している機能性表示食品や特定保健用食品は、この食品の三次機能を標榜した機能性食品に対して、その効果をパッケージに表示するための制度になります。また、機能性表示食品や特定保健用食品の申請をしていない食品であっても、様々な効果を有している機能性食品も多くあります。
食品の機能性を表示する諸制度
現在は、最も活発に開発されている機能性表示食品ですが、特定保健用食品や栄養機能食品などをご存知の方も多いかと思います。
現在、健康への働きを表示することのできる保健機能食品には、特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類があります。この3種類を保健機能食品といいます。それぞれ認定基準が異なっています。

特定保健用食品とは?
2019年現在も、機能性表示食品より売り上げ総額が大きく、我が国の健康食品を牽引した制度です。認可されている商品数は1061(~2019年1月10日)、1991年より施行されている制度です。
特定保健用食品(通称トクホ)とは?
— 食品機能学研究室 (@foodfunctionlab) 2019年6月28日
1991年より開始された制度で、主にメタボリックシンドロームや便秘などを予防する表示をしている食品が多くあります。
設立当初は厚生労働省、現在は消費者庁に届出をして、安全性や有効性の審査を受けて表示が許可されます。#栄養学 #生環 pic.twitter.com/LKVW8g7f18
消費者庁に申請をして許可を受けることになっており、企業に大きな負担が必要となり、中小企業の参入が困難であるなどが問題でした。
更に製品を人で試験を実施し、科学的に根拠を示す必要があります。
機能性表示食品は、申請して要件を満たしているか書式のチェックを受けて(事実上の審査のようになっていますが)受理される食品で、企業にその責任があることが特定保健用食品との大きな違いです。
現在までに「血糖・血圧・血中のコレステロールなどを正常に保つことを助ける」「おなかの調子を整える」「骨の健康に役立つ」などの保健機能の表示が許可されています。
特定保健用食品に関する詳細は、以下もご参照ください。
栄養機能食品とは?
コンビニエンスなどで特定保健用食品や機能性表示食品よりも製品を多く見かけるように思います。
栄養機能食品とは?
— 食品機能学研究室 (@foodfunctionlab) 2019年6月28日
ビタミンもしくはミネラルが多く含まれる食品。国が定める範囲に収める必要があります。
特定保健用食品や機能性表示食品と違って、都度、申請する必要がない(=規格基準型)ことが、企業にとって大きな利点ですが、表示も固定されてしまうことがデメリット。#栄養学 #生環
消費者庁に申請することなく表示をすることが可能ですが、主にビタミンやミネラルのみに限られます。
例)サプリメント
栄養成分ごとに1日当たりの摂取量の基準値が国によって定められている栄養成分を、その基準値内であれば国の審査の許可申請なしで該当する栄養成分の機能を表示することができます。
特別用途食品とは?
コンビニエンスストアやスーパーでは、ほとんど見かけないです。ドラッグストア等で経口補水液などを見かけることがあります。
特別用途食品とは?
— 食品機能学研究室 (@foodfunctionlab) 2019年6月28日
病気の方や高齢者など、特別な状況にある方々に適する食品。画像はえん下困難者用食品ですが、病者用や妊産婦用などの食品があります。
あまり見かけないですが、ドラッグストアでは経口補水液のOS-1がほぼ確実に置かれています。#栄養学 #生環 pic.twitter.com/0wg69KOY7h
文字通り、特別な用途のために利用される食品です。例えば、固い食品を摂取できな高齢者などのために利用される「えん下困難者用食品」や食品アレルギーの方への「アレルゲン除去食品」などがあります。